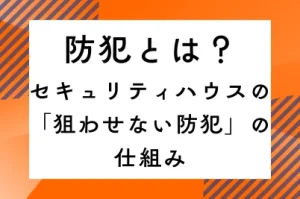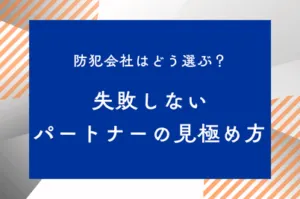2025.09.29
泥棒に侵入された後の“二次被害”とは?そもそも狙わせない防犯なら安全・安心
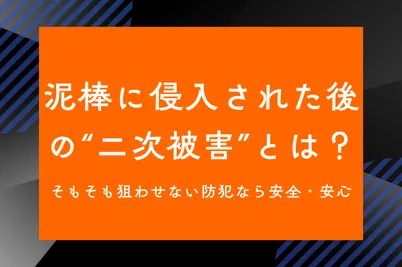
結論から言います。泥棒に入られた後、金品の被害ももちろん怖いですが、その後に放火や器物損壊などの被害が発生し、営業停止・顧客離れ・社員の退職といった“二次被害”につながる可能性があることをご存じでしょうか?特に放火は事業継続を断たれる重大リスクになります。 こうしたリスクを防ぐには、まず【無料防犯診断】で現状を知ることが第一歩です。
泥棒に入られた“その後”に何が起こるのか?
金品以上に失うものとは?
多くの経営者が「盗まれた金額」ばかりを気にしますが、実はもっと大きな損害があります。それが、信用の喪失・社員の不安・業務の混乱です。現場が一時停止すれば、納期遅れや顧客対応の遅延が発生し、会社の信用を一気に落とします。
さらに、侵入の際に窓を割ったり鍵を壊されたりするだけでなく、侵入者が逆上して放火や器物損壊を引き起こすケースもあります。火災や設備破壊によって、営業継続が不可能になった例も少なくありません。
実際にあった中小企業の「倒産寸前」事例
ある地方の製造業者では、泥棒によって事務所のPCと取引先情報が盗まれました。個人情報の流出が懸念され、取引先からの信頼が失墜。結果、3件の契約が解除され、経営は一時危機的状況に陥りました。
別の事例では、金品が見つからなかったことで犯人が逆上し、倉庫に放火。商品の在庫すべてを失い、復旧に半年以上を要しました。

なぜ「侵入=信用喪失」になるのか?
顧客・取引先が離れるかもしれない理由
「この会社、大丈夫かな?」と不安を抱かれてしまうと、取引継続をためらわれることがあるかもしれません。泥棒に入られたという事実が、「セキュリティ体制に不安がある会社」と見られてしまい、結果として長年築いてきた信頼関係が揺らぐこともあるかもしれません。
社員の不安とモチベーション低下の連鎖
泥棒が侵入したことを知った社員は、「また来るのでは?」という不安を抱えます。夜勤や残業を拒否する人も出てきて、職場の士気は大きく低下します。
泥棒の目線で考える:どんな会社が狙われるのか?

泥棒は感情で動くのではなく、冷静に「リスクとリターン」を計算しています。時間がかかりそう、目立ちそう、騒がれそう──そう思わせた時点で、ターゲットから外れるのです。
下見段階で「ここは危ない」と判断させることが、防犯成功の第一歩です。
- セキュリティ機器が見える位置にあるか?
- 警告表示やステッカーが貼られているか?
- 夜間でも明るく、死角が少ないか?
こうした“泥棒の視点”で自社を見ることが、狙わせない環境づくりの第一歩です。
泥棒について詳しく知りたい方は 泥棒とは?手口・目的・種類を解説【防犯の基礎知識】 をご覧ください。
では、具体的にどのような対策を講じれば「狙わせない」会社になれるのか? その答えが、次の“防犯の3本柱”にあります。
狙わせない防犯の3本柱:「抑止」「検知」「記録」
1. 抑止(威嚇)──これが一番大切です
犯罪者に「ここはやめておこう」と思わせる仕掛けです。防犯の成否は、侵入前にどれだけ諦めさせられるかにかかっています。
セキュリティキーパーの役割 セキュリティキーパーは、防犯の最前線に立つ装置です。視認性の高いデザイン、常夜灯、警戒表示により、下見の段階で「ここは警戒されている」と印象づけます。侵入された場合も、強力な光と音で即座に威嚇し、犯行を断念させます。
2. 検知(センサー)
侵入の瞬間をリアルタイムで検知する仕組みです。竹中エンジニアリング(TAKEX)のセンサーは高精度・誤報が少なく、外周・屋内ともに対応可能です。
👉 防犯センサーは「狙わせない防犯」の中核!仕組みと実例を紹介
3. 記録(カメラ)
証拠を残し、事後対応や犯人特定に役立ちます。カメラは単体では抑止力が弱いため、センサーや威嚇装置との連動が不可欠です。
カメラの弱点:覆面で証拠力を下げられる、破壊や向きの変更、事後対応に偏りやすい点があります。
👉 屋外防犯カメラは“証拠を残す目”─防犯の起点となるカメラ活用
だからこそ、「抑止」「検知」「記録」を組み合わせることが重要です。
狙わせない防犯について詳しく知りたい方は、防犯とは?セキュリティハウスの「狙わせない防犯」の仕組み をご覧ください
あなたの会社は大丈夫?無料の防犯診断でリスクを見える化
侵入されてから対処するのでは遅すぎます。大切なのは、最初から“狙わせない”環境を整えておくことです。防犯のプロである私たち防犯設備士が、現場の状況を丁寧に確認し、狙わせない防犯の仕組みをご提案します。
その他オススメ記事
もっと詳しく知りたい方は「防犯専門企業セキュリティハウスのトップページ」をご覧ください。