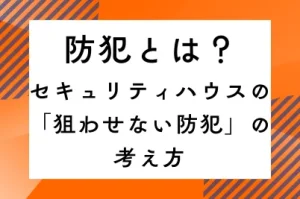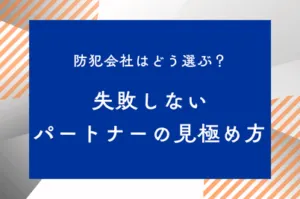2025.07.22
窓の防犯対策はガラス破壊センサー!侵入を防ぐ仕組みと選び方
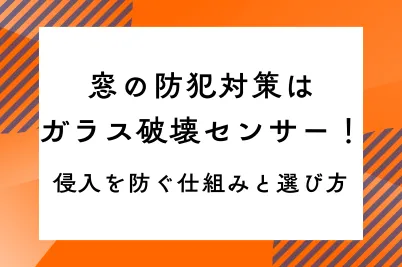
中小企業の経営者にとって、「防犯対策」は後回しにしがちなテーマかもしれません。しかし、いざ空き巣や侵入被害に遭ってしまうと、金銭的損失だけでなく、従業員や取引先との信頼関係にも大きな影響を与えます。特に注意したいのが、窓からの侵入です。
警察庁のデータによれば、空き巣の多くが窓を破って侵入しています。シャッターや鍵をかけていても、「ガラスを割って中に入る」という犯行はわずか数十秒。そこをいかに早く察知し、抑止するかが、防犯対策の分かれ道です。
この記事では、泥棒に「狙わせない環境」をつくるためのカギとなる、ガラス破壊センサーについてわかりやすく解説します。仕組みや選び方、設置のポイントまで、経営者の視点でご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
ガラス破壊センサーって何?
どんな仕組み?
ガラスが割れたときに発生する「高周波音」や「衝撃振動」を感知し、警報を鳴らす仕組みです。人に見られず侵入を試みる際でも、とっさにガラスを割ることが多く、その瞬間を検知できます。
メリットは?
- 即時検知:ガラスが割れた瞬間に反応し、警報を発します。
- 死角に強い:窓の外側に取り付ける必要がなく、死角になりにくい。
- 既存設備と併用可能:防犯カメラやアラーム、外壁センサーと一緒に使えます。
なぜ窓にセンサーが必要なのか?
窓は空き巣の侵入口ナンバーワン
日本の空き巣では、約半数が窓から侵入しています。特にガラスを割って侵入する手口は多く、犯行に時間をかけたくない犯人ほどこの手を選びます。
「狙わせない防犯」には窓対策が必須
セキュリティハウスの言葉を借りると、防犯は「狙われにくくする」ことが第一歩です。窓から侵入されそうだと思わせないようにするには、ガラス破壊センサーが非常に効果的です。
ガラス破壊センサーの選び方
検知方式
- 音響式:特殊な高周波音(ガラスが割れる音)を検知します。
- 衝撃式:ガラスに当たる衝撃振動を感知します。
→音響式・衝撃式の両方を備えたタイプが、誤検知も少なく安心です。
設置場所とカバー範囲
- 窓の上または横枠につけるのが一般的。
- 感知範囲(例:半径2〜4m)を確認し、窓全部がカバーされているかチェックを。
ガラス破壊センサーまとめ
| 型番 | 検知方式 | 主な特徴 | 適した用途 |
|---|---|---|---|
| GS‑02 | 圧電方式(衝撃検知) | ガラス面に貼り付け。180 cm範囲をカバー。シンプルで設置が容易 | 小規模オフィス・個別窓の防犯対策 |
| GS‑02C | 圧電方式(衝撃検知) | GS‑02と同機能。カールコード仕様で配線取り回しが柔軟 | 窓の配置や配線の自由度を求めるオフィス・店舗 |
| GS‑1000 | 音響式(非接触) | 水平7 m×垂直8 mの広範囲対応。感度調整・アラームメモリ・環境チェック機能搭載 | 中小企業オフィス・商業施設の誤報対策重視の防犯 |
| GS‑1100 | 音響式(非接触) | 水平8 m×垂直7 m。超音波集音でガラス破壊音を高精度検知。薄型設計・DC9–30 V対応 | オフィス・ショーウィンドウ・デザイン重視の空間 |
| GS‑2000 | 音響式(非接触) | 広範囲(8 m×7 m)をカバー。環境チェック・アラームメモリ・工具不要の感度調整機能 | 倉庫・会議室・大型ガラス面のある施設 |
📌 使い分けポイントの補足
- GS‑02/GS‑02C:コスト重視、窓1枚ごとの対策に向く。カールコード仕様は設置の柔軟性を高めたい現場に有効。
- GS‑1000:誤検知を最小限に抑えたい場合に最適。センサーの性能・信頼性ともにバランス良好。
- GS‑1100:目立ちにくさやデザイン性を重視したい空間に。ショールームや商談室などにも好適。
- GS‑2000:広範囲をまとめて守りたい現場におすすめ。工具不要の調整で施工もスムーズ。
既存設備との連携
竹中エンジニアリング製センサーや「セキュリティキーパー」などと接続できるか確認しましょう。
統合的なシステムにすることで、警報だけでなく録画や遠隔通報にも対応できます。
導入のポイントと注意点
誤報を減らす工夫
- 飛び石や風でガラスが揺れると誤作動することもあります。
- 音響+衝撃のデュアル検知方式や、感度調整機能のある製品が◎。
電源とバッテリー
- 電池式が多く、停電時にも動作します。
- 電池寿命(例:1〜2年)や交換しやすさもチェックポイントです。
設置後の動作確認
- 導入直後はテストモードを使い、実際に割れる音や軽く叩く音などを試して、検知が働くかしっかり確認しましょう。
導入効果を高める運用ポイント
- 従業員教育
センサー設置後は、音が鳴ったらどう動くか、従業員に周知・訓練しておくと安心です。 - 定期点検
半年に一度は電池残量、接続状態、警報の作動確認を。 - 他設備との連携
通報装置・照明・カメラと組み合わせれば、防犯ラインを強固にできます。
おわりに
窓からの侵入は「あってはならない事態」です。ガラス破壊センサーは、音や振動で迅速に検知し、犯行を防止する「窓の防犯の要」です。導入・運用・連携をしっかり行えば、中小企業の安全をぐっと高めることができます。ぜひ、今回のガイドを参考に、社長自ら防犯対策の一歩を踏み出してください。
本記事は「葉」の内容です。
基礎(幹)は [防犯とは?セキュリティハウスの「狙わせない防犯」の仕組み]、
展開(枝)は [防犯センサーは「狙わせない防犯」の中核!仕組みと実例を紹介]をご覧ください。
その他オススメ記事
もっと詳しく知りたい方は「防犯専門企業セキュリティハウスのトップページ」をご覧ください。